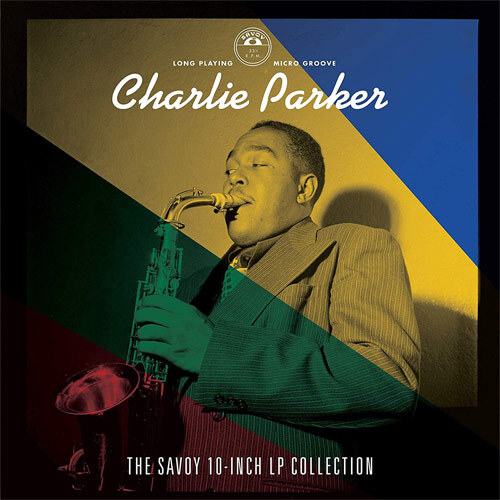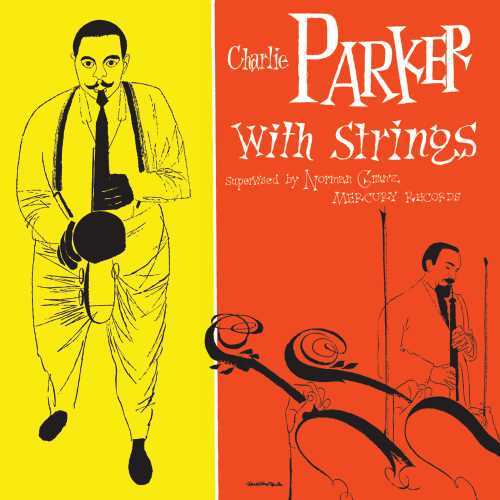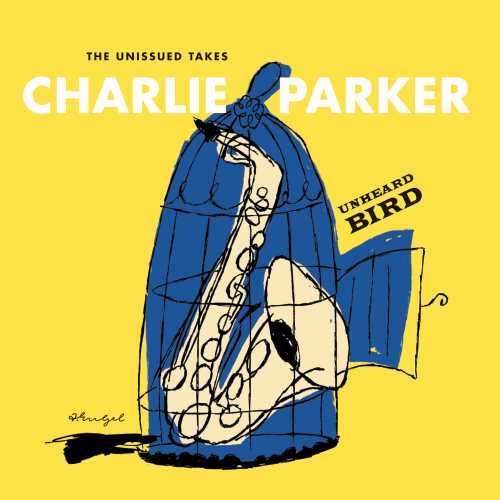分厚く豊かなサックスの音色、スピード感のかたまりのような吹きっぷり、体内にポリリズム醸成装置が埋め込まれているのではないかと思えるほどの自由自在なリズム感、超絶テクニカルなのに最大限にメロディアスで人懐っこいアドリブ・フレーズ、どんなに他のミュージシャンが煽ろうとも漂い続ける“超然”“醒め”。
ジャズは、かっこいい音楽だ。どのミュージシャンがかっこいいのかは各リスナーにとって意見が分かれるところだろうが、僕にとってその「かっこよさ」を最大限に体現している人物はチャーリー・パーカー(1920~55)に尽きる。2017年発表のトリビュート・アルバム『ザ・パッション・オブ・チャーリー・パーカー』では、キャンディス・スプリングス、メロディ・ガルドー、グレゴリー・ポーター等のヴォーカリストが、マーク・ジュリアナやダニー・マッキャスリンを含むバンドと共に“パーカーの音楽をなぞらずに、パーカーのたたずまいを現出させる”という粋なことをした。それを耳にしてチャーリー・パーカーの名を心に刻んだ21世紀の音楽ファンも多かったのではなかろうか。そして2020年、この不滅のジャズ・アイコンは生誕100年を迎えた。11月6日に登場したのは、すべて日本初リリースとなる3作品。こうしてまた新規のチャーリー・パーカー・フリークが増えていくのかと思うと、うれしくて仕方がない。

『ニュー・サウンズ・イン・モダン・ミュージック』は、“パーカーの作品は数が多すぎて何から聴いていいかわからない”と真面目に戸惑っているひとにも、“ディスク1枚でとりあえずパーカー最高のところを”と望む横着気味のひとにも喜んでもらえること間違いなしの選集。パーカー存命中、「サヴォイ」というレーベルから発売されていた10インチ(25㎝)LPレコード『ニュー・サウンズ・イン・モダン・ミュージック』(全4巻)に収められていた全曲が1枚のCDに封じ込められている。録音は1944年から48年にかけて・・・と書くと、あまりにも歳月が流れていることに驚くかもしれないけれど、はっきりいって「ぜんぜん古くない」「むしろ新鮮」。あなたの好きな後進ミュージシャンたちがよく使うフレーズが、もうこの時期にチャーリー・パーカーによって創造されていたという事実に驚くこともできるだろうし、「ドナ・リー」や「ナウズ・ザ・タイム」など今日の大スタンダード・ナンバーが最初はどういうパフォーマンスで世に出たのかを確認できる意義も大きい。僕は「韋編三絶」(いへんさんぜつ)という言葉を躊躇せず使えるぐらいにはパーカーの公式音源を繰り返し聴いてきたつもりだが、それでも今回、新たな発見があった。というのも、リマスタリング効果が驚嘆に値するほど抜群だからだ。カーリー・ラッセルやネルソン・ボイドらベーシストが送り出すヴィヴィッドなビート、「マーマデューク」でマックス・ローチが打ち出すバスドラ連打、「アー・リュー・チャ」でピアニストのジョン・ルイスが発する実に気持ちよさそうなハミング、すべて個人的には初めてしっかり聴き取れた。「ウォーミング・アップ・ア・リフ」途中の笑い声は臨場感を増し、「コ・コ」の冒頭に発生していたはずの“ピキッ”というサーフィス・ノイズ(?)は消え、当然ながらパーカーの鬼神が乗り移ったかのようなプレイにおける音色の旨みは増しに増し、この作品をきっかけに“チャーリー・パーカーの大海”に漕ぎ出していくファンは本当にラッキーだな、と、聴いていてつい遠い目をしてしまう。まさに一生もの、値千金、定価2800円+税で手に入れることのできる1000万ドルの快感、といいきってしまおう。
・Warming Up A Riff
サヴォイとの契約が終了する少し前、1948年の秋ごろからパーカーは、ノーマン・グランツ監修のもとでのレコーディングを本格化させる。それまで所属したのは「サヴォイ」にしろ「ダイアル」にしろ、ジャズを中心とするインディペンデント・レーベルだったが、グランツが提携していたマーキュリーは白人ポップスやクラシックも取り扱うメジャー・レーベルで予算にも恵まれていた。パーカーは“弦楽合奏をバックに演奏したい”と長年の願いを提案し、それは“レギュラー・グループによる録音は十分出ているのだから、今度はレコーディング独自の企画でこのサックス奏者の魅力を引き出したい”というグランツの考えとも一致した。そのプロジェクトの正規音源を集大成した2枚組が『ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス』だ。ディスク1はマスター・テイク(OKテイク)、ディスク2は別テイク(リアルタイムでは発表が見送られたテイク)で占められており、背後にがっちりアレンジが施されていようと、パーカーの“歌いっぷり”はそのときどきで自由自在であったことが改めて確認できる。
95年にウィズ・ストリングス・アルバム『パールズ』を出したサックス奏者デヴィッド・サンボーンの談話(文責デイヴィッド・リッツ)も読み逃せない。一部を抜き出してみる。
どのソロにも、途方もなく複雑な感情がこめられているのである。バード(=パーカー)の聡明なソロを採譜して分析してみると、バッハを思い出す。両者は驚くほど似ていて、自身の音楽を構築するにあたって、どちらの天才も、考えられないほど独創的な内部の論理性を発揮するのである。いちど聴いたら忘れられないこれらのメロディのバードによる演奏を聴くのは、ダイアモンドを手にするようなものだ。その宝石を手のひらの上で転がすと、数えきれないほど多くの面が光を反射する。 (訳:坂本信)
分厚いブックレットには全文、封入ライナーノーツには全訳が掲載されている。ぜひ現物を確認していただきたい。
・Just Friends
いっぽう『アンハード・バード』は、こだわりだらけの編集盤だ。55年の他界まで続いた“パーカーのノーマン・グランツ時代”は89年、10枚組CD『Bird: Complete Charlie Parker on Verve』に集大成されたはずであった。が、監修者のフィル・シャープは後日、別の倉庫に相当数の未発表音源があることを発見する。それをまとめた作品がこの“unheard”(=いまだかつて聴かれたことがない)と題された2枚組なのだ。スタジオでの音楽家どうしのやりとりをそのまま収めた場面あり、途中で演奏を止めて頭からやりなおす場面ありと、単に音楽を鑑賞する向きにはいささか敷居が高いところもあるかもしれない・・・という考えはもう古いのかもしれない。ひとつの作品(楽曲)が仕上がっていく過程を、たとえば現役人気音楽家のライヴDVDに必ずと言っていいほどついている「メイキング映像」を見るような気持でドキドキハラハラしながら楽しむ。これが2020年を生きるパーカー・ファンの生きる道ではないか。シャープ自らしたためたライナーノーツにも驚くようなエピソードがちりばめられているし(レコーディングを終えたパーカーたちは、彼の父の運転する車に乗って空港に行き、パリへ向かったなど)、パーカーのオリジナル曲とされる中でも、明らかに別種の趣を持つ「マイ・リトル・スエード・シューズ」の“原曲”に関する考察もディープすぎて開いた口がふさがらない。
・My Little Suede Shoes
都会では、いや地球中で自殺する者が増えているという。が、そう決断するのはチャーリー・パーカーのありとあらゆる音源を体内に注入しきってからでも遅くはない。ブルースのロバート・ジョンソン、ロックのジミ・ヘンドリックスに比される「永遠の生命体」、チャーリー・パーカーに乾杯!
■作品情報
『ニュー・サウンズ・イン・モダン・ミュージック』
<チャーリー・パーカー生誕100周年UHQ-CD リイッシュー>第2弾も同時リリース
『ザ・コンプリート・チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス』
『アンハード・バード:未発表テイク集』
Header image: Charlie Parker. Photo: William P. Gottlieb/Ira and Leonore S. Gershwin Fund Collection, Music Division, Library of Congress.